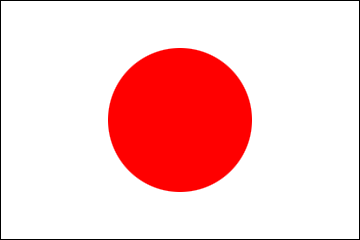安全・領事・医療情報
戸籍
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
そこで,戸籍・国籍関係の届出の主なものをあげると次の通りです。
「戸籍関係」
出生届,婚姻届,死亡届,離婚届,認知届,養子縁組届,養子離縁届,外国人との婚姻による氏の変更届
「国籍関係」
国籍選択届,国籍喪失届,国籍離脱届,国籍取得届
1.届出期限
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。
2.届出人
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
3.届出方法
在外公館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送することも可能)。
4.届出に必要な書類
(1) 出生届書(在外公館に備え付けてあります。)
(2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本
(3)同和訳文
5.必要な通数
通常それぞれ2通ですが,新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。
6.留意事項
海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。
日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは,生地主義といって,父又は母の国籍に関係なく,その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と,血統主義といって,外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。
具体的には次のような場合が考えられます。
(1) 日本人父母の間に米国,カナダ,ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合
(2)ドイツ,中国,フィリピン,フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合
(3)イラン,スリランカ等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお,父が日本人で,母がイラン人又はスリランカ人の場合は,お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので,日本国籍を留保する必要はありません)
1.日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
(1)届出人
当事者双方です。
(2)届出方法
窓口に直接届け出ます。
(3)届出に必要な書類
(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)
*証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
(4)必要通数
当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって,2通ないし4通が必要です。
2.日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。
(1)届出期限
婚姻成立日より3ヶ月以内です。
(2)届出人
当事者双方
(3)届出方法
窓口に直接届け出ます。
(4)届出に必要な書類
(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)
(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
(C)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
(5)必要通数
上記1.(4)と同様
(6)留意事項
外国の方式による婚姻の手続きについては,当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。
(1)届出期間
婚姻成立日より3ヶ月以内です。
(2)届出人
日本人当事者です。
(3)届出方法
窓口に直接届け出ます。
(4)届出に必要な書類
(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)
(B)戸籍謄(抄)本(日本人につき)
(C)当該国官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
(D)外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
(5)必要通数
日本人について,本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
(6)留意事項
外国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。